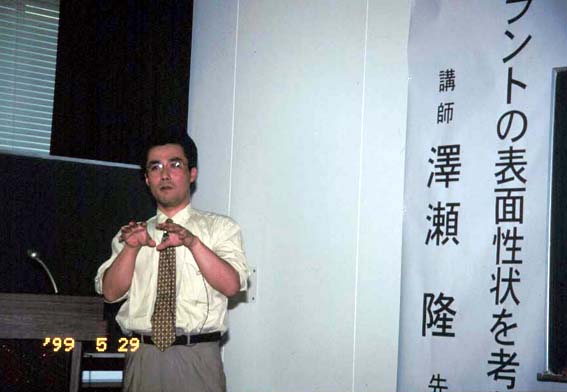
| 平成11年度第1回学術講演会 |
平成11年5月29日(土)、午後3時30分より長崎大学歯学部5階第一講義室にて、平成11年度の学術講演会を行いました。
講師には、当大学の4期生であります、澤瀬隆先生をお招きし、「インプラントの表面
性状について考える」という演題でご講演いただきました。講師の澤瀬先生は、卒業後、当大学の第一補綴科の大学院に進学され、大学院卒業後、助手として補綴学を専門にされ、1996年から1998年までの2年間スウェーデンのヨーテボリ大学に留学され、現在、当大学第一補綴科助手としてご活躍中です。
講演は基礎的研究と臨床症例を交えお話していただきました。また事後抄録を頂いておりますので以下に掲載させていただきます。
歯科インプラントによる欠損補綴法は1960年代から70年代へと歴史的変遷を経たのち、その予知性の高さと有益性から現在では歯科治療の分野で最も発展性のある項目の一つとして注目を集めるようになってきています。
今回、現在のインプラント研究において非常にホットな話題であるインプラントの表面
性状について焦点を当てこれまでの研究において理解されていることをご紹介させていただきました。
インプラントが補綴物の維持装置として機能するために欠くことのできない、顎骨との緊密な接触・結合(オッセオインテグレーション)の獲得のためには、インプラント表面
にある程度の粗さが必要で、その粗さには最適な値があることがこれまでの研究で解ってきました。氾濫するインプラントシステムの中にも、様々な技法によって粗造化が図られたインプラントが存在しますが、それらの中にはインプラントの化学的表面
組成を変化させ、元来持つチタンの優れた生体親和性を損なう可能性もあることが示唆されており、また過度な粗造化は一度インプラント周囲組織の炎症に晒されると、その後の爆発的な炎症の波及につながり、インプラントの失敗につながる危険性を孕んでいることも報告されています。さらにチタンと相並び、骨組織との親和性の高いと言われていることから、表面
のコーティング材として頻用されているハイドロキシアパタイト(HA)についても、いまだ長期的に安定なコーティング法はなく、インプラント材としての予知性には乏しいのが現状です。今後21世紀を迎えるに当たって、表面
の形状および性状を改質し、高度にコントロールしたインプラント、すなわち生体にとってのインプラント表面
の最適化が進んでいくと思われます。またそれにより能動的に周囲骨組織形成を促進させ、さらに恒久的に維持させるような組織適合型のインプラントの開発が期待されるところです。
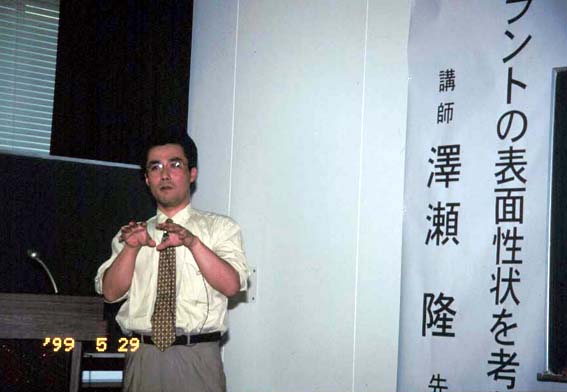 |
学術 鎌田幸治
|